2024年5月16日(木)18:30から、日本ビジネスシステムズの講演ルームおよび「Lucy’s Tokyo」(虎ノ門ヒルズステーションタワー20階)をお借りし、「新入寮生歓迎会・新社会人激励会」がハイブリッド開催(オンライン、リアルの両面開催) されました。参加人数は、OB・現役・一般参加者別で「OB20名、現役27名、一般参加者4名」合計51名、ZOOMリアル別で「Zoom1名、リアル50名」。新入寮生10名は全員が参加、新社会人 (卒寮生) も生活が変化した中、9名中4名が参加してくれました。特記事項としては
以下諸点が挙げられます。
①幹事以外のOBでは以下の方々がご出席下さいました。有難うございました。
佐藤 鉄也さん(S50工)、上島 健史さん(S56経)、泉 光一郎さん(S60文)、平栗 達也さん(S63文)、
村瀬 駿太郎さん(H30法)、川村 剛さん(R6薬)、加地 健さん(R6理工)、佐々木 綾太さん(R6理工)、
喜多 総一郎さん(R6看護)
②現舎監である大出先生、日吉学生部の関課長および担当の廣瀨さんが、昨年に続いてご参加下さり、
それぞれご挨拶下さいました。
③講演者/猪瀬 直樹先生、および奥様(女優・画家、蜷川 有紀様)が懇親会にもご参加下さいました。
なお、猪瀬 直樹先生の講演会については、以下の通りまとめました。ご一読下さい。
【猪瀬 直樹先生の講演内容】演題:いま、日本人は何をすべきか
先生の講演内容は引出しの多さから話題が多岐に亘りましたが、主なポイントは次のことでした。
1.ふるさとを創った男 (唱歌誕生と高野 辰之と岡野 貞一)、societyを人間交際 (ジンカンコウサイ)と
訳した福澤 諭吉を通じて、江戸から明治に変わっていく日本の近代化が如何に大変な作業で
あったか。
2.カズオ・イシグロ氏の作品と村上 春樹氏の作品を例に出し、(私見と断りながら)作品に「公(おお
やけ) の歴史が流れているか否か」が如何に大きな違いであるか。
3.著書「昭和16年夏の敗戦」に基づき、「正しいファクトからロジックをきちんと組み立てること」
「ファクトとロジックをもって判断していくこと」が如何に大切なことであるか。
以下、いくつかのパートを抜き出して、講演会の報告とさせて頂きます。尚、全容、詳細はYouTubeを通しでご視聴頂かないと把握できません。また、先生の著書「公(おおやけ) 日本国・意思決定のマネジメントを問う」が参考になります。是非ご視聴、ご購読下さい。
1.・・・つまり、我々の伝統文化というものにはいいところがあるけれども、近代化というのはどういうものかということを理解しておかないといけない。中国も、韓国もタイ以外はインドも含めて全部ヨーロッパの植民地になってしまった。日本は何とか
それを免れようとして急速な近代化を急いだ、もちろん一方で歪みもあった、しかし歪みが生じても近代化を急いで何とか現状を切り抜けようとした。そこまでわかれば、まずは、なぜ福澤諭吉がsocietyを何とか訳そうとしたか、その理由が見えてくる。概念がない中でも、考え出さなければいけない、彼はそういう使命感を感じていたのです。近代国家は、皆が、色々な人たちがタコ壺の壁を超えて、狭い枠を超えて、広場に出て、そして討論して物事を決めていく、こういうことがヨーロッパの近代化なのだと、そういうことを福澤は必死で考えて、(今では我々は当たり前に思っているけれども)衣を脱ぎ替えたのです。しかし、実は二重構造になっている。非常に日本的な信条というものを常に抱えている一方で、同時にその欧米的なものを身にまとっているということですね。そうやってsociety、人間交際が始まっていく訳です。でもやっぱり日本人はね、会議となると発言しないやつが多いの、来るなって言いたい。会議はね、そこで言わなきゃだめなのよ。そうやって国際社会の会議で黙ってるからやられちゃうんだよ、色々・・・。ということで、いかに福澤諭吉がsocietyの翻訳に苦労したかという話です。そのために慶應大学を創ったのだから。いいかい?、それ分かって入学してるの?(先生のこの問いかけに対し、学生はこっくりと頷く)。本当なんだよこれ、たまたま僕が話してるんじゃなくて、これ日本の尊厳の話だからね。近代化の・・・。
3.・・・それと、最後にこれで締めくくりたいんだけど、昭和16年夏の敗戦、(寮生に「戦争負けたよな」と質問、学生がもじもじしていると「もっと自信もって喋れよ」と明るく𠮟咤した後に) 、(敗戦は)昭和20年だけど、何故「昭和16年の敗戦」というテーマなのか。これは、僕が30代中頃に書いたんです、若い時にね。自分が戦争を始める前にどう考えるだろうと、結果が見えてるからね、昭和20年に負けたっていうのは。昭和16年にみんな立ち戻った時に、アメリカと戦争やるかどうか迷うよね。だって、どう考えたって向こうはでっかいよな、強そうだよな。やらない方がいいんじゃないかな、と思うのは普通だと思うんだよね。なので僕もその時にどう考えるかなと思って色々調べたんです。実は、この時、35人の30代前半の若者が集められました。総力戦研究所というところに。これはね、将来、例えば財務省だったら財務省の事務次官か財務官になるだろうとか、あるいは日銀だったら日銀の総裁になるだろとか、会社だったら会社の社長になるだろう、そういう人を35人集めたんです、総力戦研究所に。それで模擬内閣を作った。お前さん総理大臣だよ、お前さんは日銀総裁だよ、お前さんは(今経産大臣だけど)商工大臣だよ、お前さんは(今財務大臣だけど)大蔵大臣だよ、あるいは海軍大臣、陸軍大臣、そういう風に役職を割り当てて、35人で議論するんです。シュミレーションをやるんです。これからアメリカと戦争したらどうなるかってシュミレーションする。そうすると、それぞれ知らない人同士が集まるんだけど縦割りを超えて議論するわけですね、みんな頭の良い人ばっかり集まったわけ。それで、財務省だったら財務省の引き出しから、経産省だったら経産省の引き出しから自分で資料持ってくるんですね。それぞれみんな自分の会社から持ってきた。それでシミュレーションをやるんです。そうすると色々やって議論して模擬内閣で検討するわけ、外務大臣もいれば、海軍大臣もいる中で、色々やる、そうしたらね、結局結論は、日本は初め勝つけど、3年か4年経ったら負けると、最後はソ連が参戦すると、だから (実際に起こったことと)全く同じなんだ、原爆はないからね。原爆は当時作り始めたところだから、まだ予想できないよこの段階で。だから原爆は予想できないけど最後にソ連が参戦すると、参戦して日本は負けるとこまで予想できた。始めは勝つけどだんだんだんだんやって、総力戦になりながら負けてくるという風なことで、昭和16年夏にやった「昭和16年夏の敗戦」いいタイトルだろ?その時全然売れなかったんだ。その時は「ジャパン・アズ・ナンバー・ワン」がベストセラーで僕は日本の意思決定は危ないって書いてあるんだよ、ここで。歴史的に。それで今ずっと売れてる。トップセラーでね。
ということで、色々話したんだけど、まず君らは慶應義塾に来たんだから、福澤諭吉ぐらいはちゃんと読んどけよな。それで私は、なぜ福澤がわざわざ大学作ったのか、ということを語ってきた訳ね。そのためには人間交際と男女交際があって、societyはみんなが広場で自分から発言して、縦割りを超えて議論して、それでこの昭和16年夏の敗戦も各役所から来ているけれど、縦割りを超えて議論して、正しい決論も出したということです。大事なことは、今さっきのあの地震の話もそうだけど、ファクトをきちんとしてロジックをきちんと組み立てれば、少なくとも3年4年5年先は見えるってことなのね、予測できる。地震じゃないよ、我々がどういう決定事項をしていったらいいかってことは分かる、そういうことを言ってるんでね。だから間違った決定はしなくて済むんだよ。政策的には何ていうかっていうと、エビデンス・ベースド・ポリシー・メイキングっていうのね。エビデンスに基づいた政策形成ということね、それを僕が今作家をやって、(加えて)参議院議員として今日も厚生労働委員会で武見大臣と色々やり合った。例えば、「「適切に」っていうけど、適切ってなんだ」とかね、、色々言ってやり合ってきたわけ、ま、そういうことです。
この後、質疑となります。質疑も大変面白い展開となっています。YouTubeでご視聴下さい。
https://youtu.be/baFlaHBxrWg 
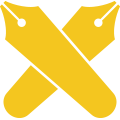 慶応義塾大学 日吉寄宿舎寮和会 情報館
慶応義塾大学 日吉寄宿舎寮和会 情報館


